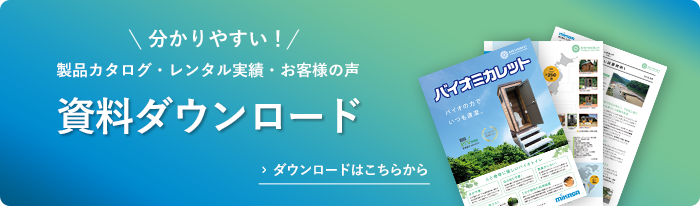広島県福山市の歴史的砂防施設「別所砂留」に、バイオトイレ【バイオミカレット®】を設置しました。市民団体・行政・民間企業が協働して実現した公民連携の取り組みです。

この度、広島県福山市の江戸時代の砂防施設「別所砂留(べっしょすなどめ)」に、弊社のバイオトイレ【バイオミカレット®】を設置させていただきました。
このプロジェクトは、地域の宝を守りたいという市民の強い想いが行政を動かし、民間企業も加わった公民連携によって実現した、特筆すべき事例です。
インフラが未整備な場所でのトイレ問題に悩む多くの市民団体や自治体の皆様にとって、課題解決の参考になることを願い詳細をご紹介します。
目次
歴史的遺産を守る人々の、長年の悩み

約300年前の古文書にも記録が残る「別所砂留」は、大小36基の石積みの砂留が現存する貴重な土木遺産です。この歴史的価値を守り、後世に伝えようと、地元の市民団体「別所砂留を守る会」の皆様が長年にわたり保全活動や見学会の開催を続けてこられました。

しかし、その活動には大きな悩みがありました。水道も電気もない山中の活動拠点には、古く衛生面でも課題のある和式の簡易トイレしかなく、特に活動に参加してくれる女性や、社会科見学で訪れる子どもたちの利用には大きな困難が伴っていました。
「守る会」の光成会長は、当時の状況をこう語ります。
作業に参加してくれる女性や、社会見学に来てくれる子どもたちが安心して使えるトイレがないことが、ずっと心苦しかった。特に子どもたちが古いトイレを見て『汚い!』と悲鳴を上げるのを聞くたびに、何とかしなければという思いを強くしていました。

さらに、設置場所は砂防法による規制区域であり、コンクリート基礎を伴う恒久的な建物の建設は許可されません。
電気・水道・バキュームカーの乗り入れもできないという厳しい制約が、トイレ環境の改善を一層困難なものにしていました。
市民の熱意が受賞に繋がり、公民連携プロジェクトへ
状況が大きく動いたのは、2016年に「別所砂留を守る会」が土木学会の「市民普請大賞」でグランプリ(日本一)を受賞したことがきっかけでした。

この快挙は地域に大きな誇りをもたらし、活動の意義が公に認められたことで、行政も本格的にトイレ課題へと乗り出します。そして福山市の枝廣市長(当時)自らが現地を視察し、問題解決への機運が一気に高まりました。
その後「守る会」、福山市、さらに廃棄物収集や施設管理を担う地元の「株式会社オガワエコノス」様が参画する公民連携の「研究会」が発足。当初、ある業者からのトイレの見積もりが2,000万円にも上り、計画は一度頓挫しかけましたが、研究会での粘り強い検討が続きました。
福山市職員の新谷様は、【バイオミカレット®】を次のように説明してくださいました。
電気・水道がなく、バキュームカーも入れないという厳しい条件下で、自己完結型で環境負荷の少ないバイオトイレが最適な解決策となりました。研究会で複数社の製品を比較検討した結果、費用面や提案内容で最も優れていたミカサさんの【バイオミカレット®】に決定しました。
電源の問題は、固定物とはならない発電機を使用することで解決。

弊社にとっても新たな挑戦となる設置方法でしたが、地域の皆様の熱意に応えるべく、全力で協力させていただきました。
人力での運搬と現地組立
しかし、最終的に大きな課題として残ったのが、トイレ本体の搬入でした。設置予定地へと続く道は、大型車両が進入できない未舗装の山道だったのです。
この難題を解決したのが、弊社製品【バイオミカレット®】が持つもう一つの特長でした。軽量で腐食に強く、高強度なステンレスではない素材を処理装置に採用し、現場での分解・組立が可能な設計となっている点です。

今回のプロジェクトでは、トイレを一度分解して福山市まで搬送し、その後、現地では部品ごとに人の手で山道を運び上げ、再び組み立てるという方法を選択しました。
搬入作業の際には、「守る会」の皆様が「私たちも運びます」と声を上げ、積極的に作業に参加してくださいました。共に汗を流しながら部品を運ぶその光景は、地域の方々の温かい協力と絆を感じさせるものでした。
※重機が入れない場所にも設置できるこの柔軟性は、山小屋や自然公園、歴史的史跡など、これまでトイレ設置を諦めていた多くの場所に新たな可能性をひらく、弊社製品の大きな強みです。
完成披露会と、地域に受け継がれるバイオトイレ
設置後の完成披露・操作説明会は、当日は小雨がぱらつくあいにくの天気でしたが、「守る会」の皆様をはじめ、福山市北部地域振興課の皆様、オガワエコノス様など、プロジェクトに関わった多くの方々にお集まりいただきました。

皆様、今後の維持管理のためにと、熱心に操作方法や注意点の説明に耳を傾けてくださいました。

さらにこの模様は中国新聞様にも取材・掲載され、地域の皆様の喜びの輪がさらに広がりました。

何よりも印象的だったのは、説明会が終わり、私たちがトイレの引き渡しを終えた直後のことです。「守る会」の皆様が、すぐにバイオトイレの外側に目隠しを増設する作業を始められたのです。

その手際の良さと行動力からは、このトイレを自分たちの手で大切に守り、育てていこうという強い意志と愛情がひしひしと伝わってきました。
単なるトイレではない、資源循環と教育の拠点へ
無事に設置と説明会が完了し、守る会の皆様からは大きな喜びの声をいただきました。
光成会長は、未来を見据えてこう語ります。
これで子どもたちも安心して見学に呼べます。そして、このトイレはただ便利なだけではありません。砂留の歴史とともに、排泄物という資源を堆肥として循環させるSDGsの取り組みを、子どもたちに伝える絶好の教材にもなると思っています。
このビジョンを行政の立場から支える福山市の新谷様も、本プロジェクトの意義と今後の展望について語ってくださいました。
これは、市が推進する『市民が主役のまちづくり』の素晴らしいモデルケースです。私たちの基本姿勢は、あくまで地域の方々の主体的な取り組みを後押しすること。今回も『守る会』の皆様の熱意が原動力となり、市は発足した研究会に負担金を支出する形で支援させていただきました。今後は、このトイレの所有権も『守る会』の皆様に移管し、地域で持続的に維持管理していただく計画です。こうした素晴らしい地域主体の活動を、これからも応援していきたいと考えています。
本プロジェクトの最大の魅力は、使用後の杉チップを堆肥として地域の花壇などで再利用する「資源循環」まで視野に入れている点です。
今後は、維持管理を担うオガワエコノス様と密に連携し、定期的なメンテナンスを通じて堆肥化のプロセスや品質に関するデータを収集・分析。この先進的な資源循環モデルの実現を、弊社としても継続的にサポートしてまいります。

福山市・守る会・ミカサでの集合写真
今回の事例は、一市民団体の熱意が行政を動かし、民間企業の技術と知恵を結集させることで、困難と思われた課題を見事に解決した輝かしい前例です。歴史的遺産の保全、インフラ未整備地域での環境整備、そして持続可能な社会の実現という、複数のテーマを同時に追求する公民連携の新たなモデルケースとして、多くの皆様の参考になれば幸いです。